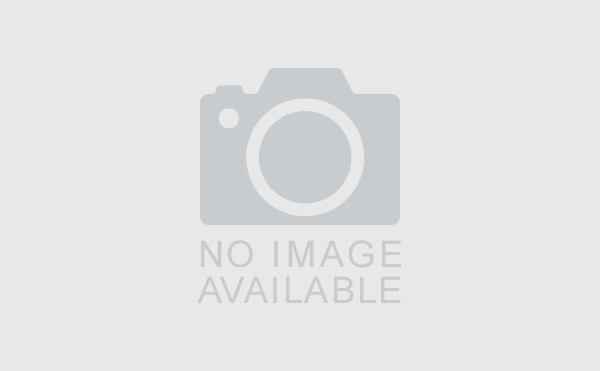農地転用制度の概要②
1.許可申請における一般基準
1-1農地転用に必要な資力及び信用があると認められること
農地転用の申請にあたっては、事業計画書に資金計画の記載が求められ、添付書類として預金の残高証明書などの提出が必要とされています。
以前はこのような書類の提出までは求められなかったため、途中で住宅建築などが頓挫してしまうようなことがよくあったそうです。また、最初から住宅建築などをするつもりなく、宅地として保有するために虚偽申請が行われた例もあります。
また、事業を行うのに必要な信用があるかについては、転用事業者の過去の事業実績などから総合的に判断されることになります。過去に無断転用などの農地法違反行為があり、それ是正されていないような場合には認められません。
1-2農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
「転用行為の妨げとなる権利」とは、法第3条第1項本文に掲げる権利であるとされています。具体的には、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益権がこれに該当することになります。
例えば、農地所有者が農地を転用しようとする場合、その農地を誰かに貸しているとすれば、その人の同意を得ておく必要があるということです。
また、転用行為を実行する人は、必ずしも所有者であるとは限りません。例えば賃借権の設定を受けてそこで農業を行っている者が、農地転用をする場合には、当然のことながら所有者の同意が必要です。
ところで、「転用行為の妨げとなる権利」には抵当権が入っていないことには注意が必要です。抵当権が設定されている農地の転用の場合、5条申請で農地の所有権が移転すると、新所有者は抵当権付きの土地を購入することになります。そのため、通常は農地転用に際し、事前に抵当権を抹消することがほとんどです。
しかしながら、これはあくまでも民間人同士の問題であって、農地転用の許可という公法上の問題には影響を及ぼしません。ですので、仮に抵当権付きの農地であっても、それだけの理由で転用(5条申請)が不許可となることはありません。
ただし、申請に係る農地に抵当権が設定されている場合や所有権移転請求権保全の仮登記が付されている場合は、農地転用実現の不安定要因であることから、抹消するか、関係者が同意していることを確認することが望ましいとされている自治体あります。
1-3農地転用の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること
農地法では、資産保有目的での農地の所有をみとめていません。農地転用の許可を受けた際には、申請時に提出した事業計画に従って、遅滞なく、目的の用途のために使用しなければなりません。
の要件を満たしているかどうかの判断になるのが、転用事業の実施にあたって必要な、農地法以外の他の法令との調整が調っているかどうかになります。
申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。)により義務付けられている行政庁との協議を行っていない場合については、申請に係る農地を申請に係る用途に供することが確実と認められないと判断することとされています。
1-4申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされる見込みがあること
産業廃棄物の処分施設を建設しようとする場合など、役所の許認可が必要な事業を実施しようとする場合、その事業についての許可等が下りる見込みがなければ、農地転用の許可がなされることはありません。
1-5申請に係る事業の施行に関して法令により義務づけられている行政庁と協議を行っており、支障がない見込みがあること
許認可が必要な事業ではないとしても、法令によって役所との協議や届出が義務付けられているものがあります。農地転用の許可の後、遅滞なく転用事業に着手するためには、必要な協議等を先に済ませておく必要があります。
1-6申請に係る農地と一体として、申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがあること
例えば、建築物の敷地にするために土地を購入するような場合には、農地以外の土地を農地と一体として購入することがあります。この場合、一体として利用する他の土地が利用できないとなれば、農地転用を受けた土地も利用不可能となってしまいます。
そのため、事業計画において農地以外の土地が含まれている場合には、その土地が本当に利用できるかということが審査の対象となります。
1-7申請に係る農地の面積が、申請に係る事業の目的からみて適正と認められること
農地法の目的は農地の保全と食料の安定供給ですので、転用する農地面積は、目的に応じて、最小限度である必要があります。
また、類似施設のない施設の転用規模については、事業計画書などにおける必要性及び具体性から合理的であるか否かを判断するとされています。
1-8申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみを目的としないものであること
農地転用の許可は、農地を宅地に変更するためだけになされるものではなく、建築物の建築などの具体的な転用事業に対してなされるものです。従って、土地の造成のみを目的とするような場合には許可を受けることができません。
申請者が工場や住宅その他の施設の建築のための土地の造成のみを行い、自らが施設の建築をせずに当該土地を処分し、申請者以外の者が施設を建築する場合、この申請は「土地の造成のみを目的とするもの」と評価されることになります。